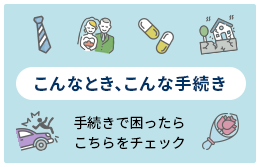貯金事業・詳細
1. 積立方法
1. 定時積立
毎月の給料から一定額を天引きします。
2. ボーナス積立
6月・12月のボーナスから一定額を天引きします。
- ※令和2年4月1日から臨時積立を休止しています。
2. 積立金額
1,000円単位です。
3. 申込・変更
「共済貯金加入申込書」に必要事項を記名・押印のうえ、所属所の共済事務担当課へ提出してください。共済組合に届いた月の翌々月から積立開始となります。
共済貯金は、退職月の末日に解約する必要がありますので、任用期間の短い方は申し込みの際に、ご注意ください。
- ※積立金額の変更は、「共済貯金変更依頼書」を所属所の共済事務担当課に提出し、共済組合に届いた月の翌々月から変更となります。
非課税の取扱い(マル優制度)
共済貯金は、一般の貯金と同様に課税扱いとなりますが、下記の場合は、貯金者の申し出により非課税扱いにすることができます。
「非課税貯蓄申告書」に必要事項を記入し、下記申告事項が確認できる書類及び個人番号が確認できる書類を添付の上、所属所を経由して共済組合に提出してください。
- 1. 貯金者が障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金の受給者)である場合
- 2. 貯金者が遺族基礎年金等の受給者(妻)である場合(注)
- 3. 貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合(注) 等
- ※非課税限度額は、共済貯金と他の金融機関への申告額を合算して350万円となります。
- (注)全額支給停止または支給終了している場合は不該当となります。(一部支給停止の場合は適用を受けられます)
4. 一部払戻し・解約
「共済貯金一部払戻請求書」または「共済貯金解約請求書」に必要事項を記名・押印のうえ、所属所の共済事務担当課へ提出してください。
1. 一部払戻し(毎月2回)
毎月15日までに共済組合に届いた請求書についてはその月の末日に、16日から末日までに共済組合に届いた請求書については翌月の15日に給付金等受取口座へ送金します。
- ※一部払戻しの限度額は、送金日の前月末の残高までとなります。
- ※送金日が休日の場合は、一部払戻し、解約ともにその前営業日となります。
2. 解約
毎月15日までに共済組合に届いた請求書について、その月の末日に給付金等受取口座へ送金します。
- ※送金日が休日の場合は、一部払戻し、解約ともにその前営業日となります。
5. 残高通知
毎年3月・9月末基準で、その間の積立・一部払戻し・利息等を記録した残高通知書を作成し、翌月(4月・10月)に所属所経由で貯金者宛に通知しています。
なお、残高通知書の再発行はできませんので、大切に保管して下さい。
6. 送金口座
送金口座は共済組合の給付金等受取口座です。
送金先の変更をする場合は「組合員申告書」を提出してください。
- ※一部払戻しまたは解約請求と併せて送金口座を変更される場合は、必ず「組合員申告書」の写しを「共済貯金一部払戻請求書」または「共済貯金解約請求書」に添付してください。
7. 共済貯金とペイオフ
ペイオフとは、金融機関が経営破綻した時、1金融機関ごとに合算して、預金者1人につき元本1千万円までと破綻日までの利息(ただし、1千万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。)を保護する制度です。
共済組合が、各月の共済貯金の払戻しや解約に備えて利用している普通預金や定期預金が対象となります。
このため、共済組合は、取引金融機関の自己資本比率や格付などを確認し、リスク管理に努めており、共済組合が行っている債券運用についても、購入時・購入後、格付などを情報収集し、リスク管理に努めています。
また、共済組合は、不測の事態に備え、欠損金補てん積立金を積立てています。令和6年度の積立金額は約92億円であり、貯金総額の約8%を見込んでいます。